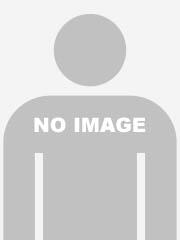
プロフィール
| 生年月日 | 元和8年8月16日(1622年) |
|---|---|
| 没年 | 貞享2年9月26日(1685年) |
| 職業等 | 兵学者 儒学者 |
| 出身 | 福島県 |
| ゆかりの地 |
経歴
山鹿素行は、会津若松で父貞以の子として生まれた。寛永4年(1627)に一家をあげて江戸に移ったが、この頃から漢籍を学び、9歳で林羅山に入門した。和学・歌学・神道・武芸・兵法など、様々な分野の修業をしたが、若い段階では兵学を主に学んでいた。諸大名からの招請があったものの、なかなか交渉が成立せず、幕臣への登用も成功しなかったが、晩年まで幕臣への夢を抱きつづけたとされている。21歳で結婚。妻は法名浄智。
承応元年(1652)に播磨国赤穂藩に仕え、翌年には赤穂城の築城設計に関わったが、万治3年(1660)にはその職を辞し、赤穂藩から離れている。この頃から現実生活に役立つ学問を追究し始め、寛文2年(1662)頃に幕府有力者であった会津藩主保科正之の信奉する朱子学を批判した新しい学問体系を構築し、同5年に『聖教要録』を刊行した。このため幕府から赤穂への流罪を宣告されたが、正之が没した3年後には赦免されている。
その後は浅草田原町に居住し、「積徳堂」を開いて『易経』にならった象数の原理とされる『原源発機』をまとめ、儒学の徳治主義を否定した『治平要録』なども著している。
貞享2年(1685)に64歳で病没し、牛込弁天町(東京都新宿区弁天町1番地)の雲居山宗参寺に葬られた。同寺には両親・素行夫人・嫡男藤助などの墓もある。
出典 『日本大百科全書』『国史大辞典』「新宿・史跡文化財散策マップ」「新宿の文化財 新宿文化財ガイド2013」
承応元年(1652)に播磨国赤穂藩に仕え、翌年には赤穂城の築城設計に関わったが、万治3年(1660)にはその職を辞し、赤穂藩から離れている。この頃から現実生活に役立つ学問を追究し始め、寛文2年(1662)頃に幕府有力者であった会津藩主保科正之の信奉する朱子学を批判した新しい学問体系を構築し、同5年に『聖教要録』を刊行した。このため幕府から赤穂への流罪を宣告されたが、正之が没した3年後には赦免されている。
その後は浅草田原町に居住し、「積徳堂」を開いて『易経』にならった象数の原理とされる『原源発機』をまとめ、儒学の徳治主義を否定した『治平要録』なども著している。
貞享2年(1685)に64歳で病没し、牛込弁天町(東京都新宿区弁天町1番地)の雲居山宗参寺に葬られた。同寺には両親・素行夫人・嫡男藤助などの墓もある。