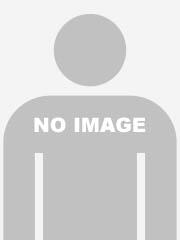
プロフィール
| 生年月日 | 明治3年2月18日(1870年) |
|---|---|
| 没年 | 昭和8年7月14日(1933年) |
| 職業等 | 劇作家、舞台監督(演出家) |
| 出身 | 宮城県生まれ |
| ゆかりの地 |
|
経歴
陸前塩釜(現・宮城県)に生まれる。本名・真玄。号は松葉、大久保二八、駿河町人とも。明治20年に上京して、国民英学会に入る。この頃から歌舞伎に傾倒する。坪内逍遥に師事し、24年から第一次「早稲田文学」編集に携わり戯曲・小説を書き始めた。27年脚本「昇旭(のぼるあさひ)朝鮮太平記」を読売新聞に発表する。30年、万朝報の記者に転身する。
初代市川左団次のために書いた『悪源太』で劇壇に注目される。この作品は、演劇改良運動の影響を受けて、劇場とは独立した作家が書いた新歌舞伎の皮切りとなった。初代左団次の死後は、明治座を引き継いだ27歳の長男・二代目左団次を助け、39年渡欧した際には呼び寄せ、ヨーロッパの演劇を学ばせるなど、俳優の指導にあたった。
二度の外遊経験を生かして新劇風経営にたずさわり、松竹の舞台監督・顧問を務めた。訳著脚本は140余種に及ぶ。また、大正2年に河合武雄と提携して公衆劇団を興した。下落合で没す。
初代市川左団次のために書いた『悪源太』で劇壇に注目される。この作品は、演劇改良運動の影響を受けて、劇場とは独立した作家が書いた新歌舞伎の皮切りとなった。初代左団次の死後は、明治座を引き継いだ27歳の長男・二代目左団次を助け、39年渡欧した際には呼び寄せ、ヨーロッパの演劇を学ばせるなど、俳優の指導にあたった。
二度の外遊経験を生かして新劇風経営にたずさわり、松竹の舞台監督・顧問を務めた。訳著脚本は140余種に及ぶ。また、大正2年に河合武雄と提携して公衆劇団を興した。下落合で没す。