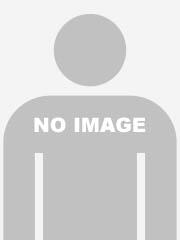
プロフィール
| 生年月日 | 天保10年3月17日(1839年) |
|---|---|
| 没年 | 明治25年6月9日(1892年) |
| 職業等 | 浮世絵師 |
| 出身 | 江戸 |
| ゆかりの地 |
経歴
芳年は天保10年に江戸新橋の商家・吉岡金三郎(後に兵部と改名)の次男として生まれた。通称は米次郎と呼ばれた。嘉永3年(1850)歌川国芳の門をたたく。その三年後錦絵の処女作とされる「文治元年平家の一門亡海中落入る図」を出版している。
嘉永6年に黒船が来航して以降、政治的混乱、コレラの流行、百姓一揆や打ちこわしといった討幕運動の高まりを経て、明治維新へと向かっていく苛烈な時代であった。こうした時代を背景に芳年が描いたのは「血みどろ絵」と称される作品群である。師国芳の武者絵を踏襲しながら、朱色に膠をまぜて光沢を与えた血の質感は、後に三島由紀夫が「飽くなき血の嗜慾」と評する独特な世界感を作り出した。その表現の極致といわれるのが、兄弟子落合芳幾との共作「英名二十八衆句」であり、上野戦争を題材にしたとされる「魁題百撰相」である。
明治5年に神経衰弱を患うが翌年に回復、大きく蘇ることを祈念して「大蘇」と号を変えた。同8年に「郵便報知新聞」に入社してからは、報道メディアの世界が活動の場になっていく。その後も「絵入自由新聞」「やまと新聞」などで、当時の風俗・世相の記事や小説の挿絵を描いている。こうした時事的な錦絵を描く一方で、「大日本名将鑑」をはじめとした歴史画を続々と刊行して人気を博した。
50歳を目前に芳年の芸術は円熟期を迎え、揃物「月百姿」「新撰東錦絵」や竪二枚続「芳流閣両雄動」といった秀作を世に送り出していった。晩年も制作意欲は衰えることなく精力的に活動するものの、同24年に再び神経の病を患い入院する。その後退院して本所区藤代町で静養していたが同25年に54歳で没した。
現在、専福寺(新宿6丁目)にある墓は、昭和46年に建て替えられたものであり、碑銘は芳年を愛した経済学者であり東京国立博物館長を務めた高橋誠一郎の筆になる。
出典 岩切友里子編著『芳年』(平凡社2014)新人物往来社編『衝撃の絵師月岡芳年』(新人物往来社2011)三島由紀夫「序にかへて(「血の晩餐―大蘇芳年の芸術 別冊」)」『三島由紀夫全集36』(新潮社2003)新宿区地域文化部文化国際課編集『新宿文化絵図 新宿まち歩きガイド 第二版』(新宿区地域文化部文化国際課2010)
嘉永6年に黒船が来航して以降、政治的混乱、コレラの流行、百姓一揆や打ちこわしといった討幕運動の高まりを経て、明治維新へと向かっていく苛烈な時代であった。こうした時代を背景に芳年が描いたのは「血みどろ絵」と称される作品群である。師国芳の武者絵を踏襲しながら、朱色に膠をまぜて光沢を与えた血の質感は、後に三島由紀夫が「飽くなき血の嗜慾」と評する独特な世界感を作り出した。その表現の極致といわれるのが、兄弟子落合芳幾との共作「英名二十八衆句」であり、上野戦争を題材にしたとされる「魁題百撰相」である。
明治5年に神経衰弱を患うが翌年に回復、大きく蘇ることを祈念して「大蘇」と号を変えた。同8年に「郵便報知新聞」に入社してからは、報道メディアの世界が活動の場になっていく。その後も「絵入自由新聞」「やまと新聞」などで、当時の風俗・世相の記事や小説の挿絵を描いている。こうした時事的な錦絵を描く一方で、「大日本名将鑑」をはじめとした歴史画を続々と刊行して人気を博した。
50歳を目前に芳年の芸術は円熟期を迎え、揃物「月百姿」「新撰東錦絵」や竪二枚続「芳流閣両雄動」といった秀作を世に送り出していった。晩年も制作意欲は衰えることなく精力的に活動するものの、同24年に再び神経の病を患い入院する。その後退院して本所区藤代町で静養していたが同25年に54歳で没した。
現在、専福寺(新宿6丁目)にある墓は、昭和46年に建て替えられたものであり、碑銘は芳年を愛した経済学者であり東京国立博物館長を務めた高橋誠一郎の筆になる。