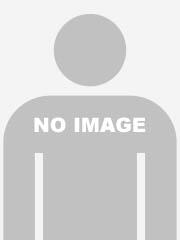
プロフィール
| 生年月日 | 明治7年7月16日(0年) |
|---|---|
| 没年 | 昭和16年8月27日(0年) |
| 職業等 | 伯爵夫人・「ヨーロッパ統一の母」 |
| 出身 | 東京都 |
| ゆかりの地 |
|
経歴
クーデンホーフ光子(青山みつ)は佐賀県出身の商人である父青山喜八と母津彌の三女として明治7年牛込納戸町で生まれた。幼少頃は町娘のたしなみとして琴や三味線といった習い事を広く習得していった。明治14年に東京芝で開業した和風社交場「紅葉館」において、お座敷女中として働く中で多彩な教育や仕事に対する姿勢を身につけ、明治24年に家に戻った。光子は日本人女性としては背が高く、美しい容姿だったという。
翌明治25年、将来の夫となるハインリッヒ・クーデンホーフ=カレルギー伯爵がオーストリア・ハンガリー駐日公使として日本に赴任する。当時ハンガリー公使館が牛込納戸町にあり伯爵が光子の父の店に訪れたことが二人の出会いになったと思われる。また伯爵が納戸町の坂の路地で落馬したところを光子が助け看病したという逸話も残されている。二人はその後結婚するが、両家から猛反対をうけ、光子は実家青山家から勘当されている。結婚後市谷加賀町にある洋館に移り住み、同26年に長男ハンス(光太郎)を同27年に次男リヒャルト(栄次郎)を生む。同29年、夫ハインリッヒが帰国するに伴いオーストリアに出発することとなる。渡欧に先立ち皇居での宮中参賀の拝謁を許されている。後日皇后陛下から「どんな場合にも日本人として誇りを忘れないように」というお言葉を賜り、象牙の扇子をいただいた。
オーストリアに着いてからは夫の故郷であるロンスペルクで暮らし、7人の子どもの母となった。光子にたいする周囲の目は厳しかったが、語学や算術、立ち居振る舞いなどヨーロッパ流の教育を学んでいく。明治39年、夫ハインリッヒが急逝する。夫の遺言により莫大な遺産相続と子ども達の教育責任を託されることになる。ウィーンのマキシング通りに移住した光子は、亡夫の意志を継いで子どもたちにヨーロッパ人として最高峰の教育を受けさせた。その後再び日本の地を踏むことなく、昭和16年にウィーン郊外でその生涯を閉じた。
光子が育てた7人の子どもたちは、優れた才能を発揮してそれぞれの分野で活躍した。特に次男リヒャルトは『パン・ヨーロッパ』を著し、ヨーロッパ共同体思想の創始者となったことで有名。彼の運動が今日のEU統合に発展したことから「ヨーロッパ統一の母」ともいわれる。
出典 木村毅著『クーデンホーフ光子伝』(鹿島出版会1986)新宿女性史研究会編『続 新宿ゆかりの女性たち』(新宿女性史研究会2002)折井美耶子編『新宿歴史に生きた女性一〇〇人』(ドメス出版2005)新宿区地域文化部文化国際課編集『新宿文化絵図 新宿まち歩きガイド 第2版』(新宿区地域文化部文化国際課2010)
翌明治25年、将来の夫となるハインリッヒ・クーデンホーフ=カレルギー伯爵がオーストリア・ハンガリー駐日公使として日本に赴任する。当時ハンガリー公使館が牛込納戸町にあり伯爵が光子の父の店に訪れたことが二人の出会いになったと思われる。また伯爵が納戸町の坂の路地で落馬したところを光子が助け看病したという逸話も残されている。二人はその後結婚するが、両家から猛反対をうけ、光子は実家青山家から勘当されている。結婚後市谷加賀町にある洋館に移り住み、同26年に長男ハンス(光太郎)を同27年に次男リヒャルト(栄次郎)を生む。同29年、夫ハインリッヒが帰国するに伴いオーストリアに出発することとなる。渡欧に先立ち皇居での宮中参賀の拝謁を許されている。後日皇后陛下から「どんな場合にも日本人として誇りを忘れないように」というお言葉を賜り、象牙の扇子をいただいた。
オーストリアに着いてからは夫の故郷であるロンスペルクで暮らし、7人の子どもの母となった。光子にたいする周囲の目は厳しかったが、語学や算術、立ち居振る舞いなどヨーロッパ流の教育を学んでいく。明治39年、夫ハインリッヒが急逝する。夫の遺言により莫大な遺産相続と子ども達の教育責任を託されることになる。ウィーンのマキシング通りに移住した光子は、亡夫の意志を継いで子どもたちにヨーロッパ人として最高峰の教育を受けさせた。その後再び日本の地を踏むことなく、昭和16年にウィーン郊外でその生涯を閉じた。
光子が育てた7人の子どもたちは、優れた才能を発揮してそれぞれの分野で活躍した。特に次男リヒャルトは『パン・ヨーロッパ』を著し、ヨーロッパ共同体思想の創始者となったことで有名。彼の運動が今日のEU統合に発展したことから「ヨーロッパ統一の母」ともいわれる。