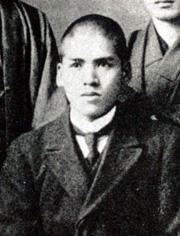
プロフィール
| 生年月日 | 明治16年12月23日(1883年) |
|---|---|
| 没年 | 昭和41年6月7日(1966年) |
| 職業等 | 評論家・哲学者 |
| 出身 | 愛媛県生まれ |
| ゆかりの地 |
|
経歴
安倍能成は、愛媛県松山市に医師安倍義任の八男として生まれた。松山中学を卒業後、明治35年に第一高等学校に入学し、 野上豊一郎、小宮豊隆、岩波茂雄らを知る。東京帝国大学哲学科に進学すると、ケーベル、波多野精一らに学ぶとともに、40年頃から漱石山房に出入りをはじめ、漱石主宰の「朝日文芸欄」「ホトトギス」にも執筆をした。喜久井町にある漱石生誕の地の記念碑は、能成の筆によるものである。
一高時代の同窓には藤村操がおり、操の自殺に衝撃を受け人生問題に苦しんだ(後に操の妹の恭子と結婚している。)卒業後は慶応義塾大学、法政大学教授など務め、大正13年にヨーロッパに留学した。この間、ニーチェ、カントなどの翻訳、『西洋 古代中世哲学史』などの他、『思想と文化』『山中雑記』など評論や随筆集を刊行した。帰国後は、京城帝国大学教授、一高の校長を務めた。この間にもカント『宗教哲学』『スピノザ倫理学』などを執筆、西洋哲学 の紹介につとめると同時に、『朝暮抄(ちょうぼしょう)』『時代と文化』などの随筆集も出版し、能成の 代表作となっている。
戦後は文部大臣となり、教育基本法と六三制の骨子を作るために尽力した。昭和21年10月、学習院長に就任、23年に は生成会同人となって、雑誌「心」の編集にも携わった。33年下落合に転居し、41年に亡くなるまで、晩年をこの地で過ごした。
出典:新宿ゆかりの文学者
一高時代の同窓には藤村操がおり、操の自殺に衝撃を受け人生問題に苦しんだ(後に操の妹の恭子と結婚している。)卒業後は慶応義塾大学、法政大学教授など務め、大正13年にヨーロッパに留学した。この間、ニーチェ、カントなどの翻訳、『西洋 古代中世哲学史』などの他、『思想と文化』『山中雑記』など評論や随筆集を刊行した。帰国後は、京城帝国大学教授、一高の校長を務めた。この間にもカント『宗教哲学』『スピノザ倫理学』などを執筆、西洋哲学 の紹介につとめると同時に、『朝暮抄(ちょうぼしょう)』『時代と文化』などの随筆集も出版し、能成の 代表作となっている。
戦後は文部大臣となり、教育基本法と六三制の骨子を作るために尽力した。昭和21年10月、学習院長に就任、23年に は生成会同人となって、雑誌「心」の編集にも携わった。33年下落合に転居し、41年に亡くなるまで、晩年をこの地で過ごした。