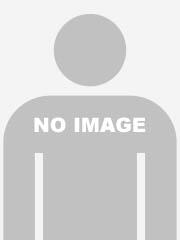
プロフィール
| 生年月日 | 明治16年12月14日(1883年) |
|---|---|
| 没年 | 昭和44年4月26日(1969年) |
| 職業等 | 武道家、合気道開祖 |
| ゆかりの地 |
|
経歴
植芝盛平は、和歌山県西牟婁郡(現・田辺市)に植芝与六の長男として生まれた。明治35年、19歳で上京し、「植芝商会」を設立し、商いをしながら武道に興味を持つ。同年、幼馴染みの糸川はつと結婚。和歌山第六十一連隊の伍長として日露戦争に出征するが、その合間に堺市の中井正勝道場に通って後藤派柳生流柔術の免許を受けた。その後も講道館柔道を学んでいたが、同43年に大いなる志を持って北海道白滝原野開拓の一団を組織し、みずから団長となって入植した。大東流柔術師範であった武田惣角に師事し、大 正5年に免許皆伝を授かっている。
大正8年、父の危篤を聞き、帰郷する途中の京都府綾部で大本教の出口王仁三郎と出会って感銘を受けた。翌年、父・与六の逝去後、家族で綾部へ移住し、道場「植芝塾」を開いた。出口から預かった土地を開墾し、武術の教授ととともに「武農一如」を掲げるようになった。この頃から一般には「植芝流合気武術」の名で知られるようになった。
大正13年には満州に出向き、その帰国後の翌年、海軍大将竹下勇の招請によって単身上京した。昭和2年になると家族で上京し、芝白金猿町の借家を居住地とし、近隣の島津公爵邸下屋敷の玉突き場を改造して道場とした。
昭和5年に牛込若松町の旧小笠原家下屋敷跡を借り受け、新道場の建設を進め、翌年4月に同町の現在地に「皇武館」道場として発足した。それ以降も「皇武館」道場のみならず、東京や大阪などの各道場を駆け回っていた。同17年に「合気道」と名乗ることとなる(19年という説もある)。健康状態の悪化や戦局の悪化などから、妻のはつとともに離京。同10年頃から少しずつ購入していた茨城県岩間の地へ赴く。「武農一如」の実現を目指し、「合気苑」の名のもとに、新たな開拓と合気神社の建立に勤しむこととなる。牛込若松町の「皇武館」は後継の吉祥丸に任された。
昭和18年、合気神社建立。同20年の終戦直後には、合気修練道場が完成した。
昭和23年2月、財団法人皇武会を改組し、財団法人合気会が発足。同35年に紫綬褒章を受章。同39年に武道界での功績をたたえ、「勲四等旭日小綬章」を受章。同43年1月、東京都新宿区若松町に新本部道場が落成し、現在に至る。同年10月、日比谷公会堂において最後となる公開演武を披露した。翌44年に満86歳で死没。「正五位勲三等瑞宝章」を授与される。
出典 植芝吉祥丸編『植芝盛平生誕百年 合気道開祖』(講談社1983)植芝吉祥丸『合気道開祖 植芝盛平伝』(出版芸術社2016)大宮司郎『開祖 植芝盛平の合気道』(柏書房2005) 『日本人名大辞典』(講談社2001)『日本大百科全書』(小学館1984)『日本武術・武道大事典』(勉誠出版2015)
大正8年、父の危篤を聞き、帰郷する途中の京都府綾部で大本教の出口王仁三郎と出会って感銘を受けた。翌年、父・与六の逝去後、家族で綾部へ移住し、道場「植芝塾」を開いた。出口から預かった土地を開墾し、武術の教授ととともに「武農一如」を掲げるようになった。この頃から一般には「植芝流合気武術」の名で知られるようになった。
大正13年には満州に出向き、その帰国後の翌年、海軍大将竹下勇の招請によって単身上京した。昭和2年になると家族で上京し、芝白金猿町の借家を居住地とし、近隣の島津公爵邸下屋敷の玉突き場を改造して道場とした。
昭和5年に牛込若松町の旧小笠原家下屋敷跡を借り受け、新道場の建設を進め、翌年4月に同町の現在地に「皇武館」道場として発足した。それ以降も「皇武館」道場のみならず、東京や大阪などの各道場を駆け回っていた。同17年に「合気道」と名乗ることとなる(19年という説もある)。健康状態の悪化や戦局の悪化などから、妻のはつとともに離京。同10年頃から少しずつ購入していた茨城県岩間の地へ赴く。「武農一如」の実現を目指し、「合気苑」の名のもとに、新たな開拓と合気神社の建立に勤しむこととなる。牛込若松町の「皇武館」は後継の吉祥丸に任された。
昭和18年、合気神社建立。同20年の終戦直後には、合気修練道場が完成した。
昭和23年2月、財団法人皇武会を改組し、財団法人合気会が発足。同35年に紫綬褒章を受章。同39年に武道界での功績をたたえ、「勲四等旭日小綬章」を受章。同43年1月、東京都新宿区若松町に新本部道場が落成し、現在に至る。同年10月、日比谷公会堂において最後となる公開演武を披露した。翌44年に満86歳で死没。「正五位勲三等瑞宝章」を授与される。