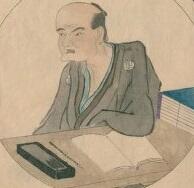
プロフィール
| 生年月日 | 寛延2年3月3日(1749年) |
|---|---|
| 没年 | 文政6年4月6日(1823年) |
| 職業等 | 狂歌師・戯作者・漢詩作者・考証随筆家 |
| 出身 | 江戸牛込中御徒町生まれ |
| ゆかりの地 |
|
経歴
大田南畝は、寛延2年(1749年)江戸牛込中御徒町に生まれた。父は幕府の御徒(おかち)として番所に勤務する吉左衛門正智、母は利世(りよ)で、貧しい家庭環境であった。
当時、下級の幕臣が貧困から脱却する唯一の方法は、学問を身につけ、登用試験である学問吟味に合格して役に就くことであった。南畝もこのような志を抱いて学問に励むべく、8歳の時には多賀谷常安に漢文の素読を学ぶ。南畝の俊秀ぶりに、多賀谷は自身の師・内山賀邸(がてい)のもとで学ぶように勧め、15歳で入門。内山は、江戸六歌仙といわれた和歌の名手であり、学問は和文漢文を兼ね、狂歌も好んでよむ人であった。永井荷風が「南畝が諧謔(かいぎゃく)の天才を夙(つと)に狂歌狂詩の類に発揚したるは其師(そのし)賀邸の薫化(くんか)によれるや明なり」と評したように、南畝の狂歌・狂詩・狂文に関する才能には賀邸門下のおおらかな気風が影響していよう。なお、明和2年(1765)には父に同じく御徒として出仕している。
明和3年(1766年)、18歳にして最初の著作『明詩擢材(みんしてきざい)』を出版する。この書は中国の明詩(みんし)を題材にした作詩の用語集で、幼い頃から漢詩文に親しんできた南畝らしい著作である。この頃、荻生徂徠(おぎゅうそらい)の高弟・太宰春台(だざいしゅんだい)に学んだ松崎観海(かんかい)に入門、漢学をより深く学ぶ。
順調に儒者への道を歩んでいたが、戯作文学者としても名を馳せていた平賀源内と出会い、『寐惚先生文集(ねぼけせんせいぶんしゅう)』(明和4年・1767年)を刊行することで狂詩・狂詩作者としての道を歩むこととなった。世相をするどく指摘したこの書が、爆発的人気を博したからである。
以降、『唐詩選』のパロディー『通詩選』、洒落本『甲駅新話(こうえきしんわ)』、狂歌集『万載狂歌集』などを発表するが、一転、寛政6年(1794年)には学問吟味を首席で合格して支配勘定となり、大阪銅座詰、長崎奉行所詰を歴任、御徒身分からの脱却を実現した。
文政3年(1820年)、詩集『杏園詩集』を出版する。日野龍夫が「南畝は、青年期に託した浪漫的な夢を、いつまでも捨てなかったのである」と述べているように、晩年にさしかかった南畝としては自身の著作を遺したいと考えたのであろう。文政6年(1823年)4月、死去。墓所は日蓮宗本念寺(文京区白山)である。
出典:『大田南畝―詩は詩佛書は米庵に狂歌おれ―』 沓掛良彦著 2007年(ミネルヴァ書房)、『朝日歴史人名事典』 1994年(朝日新聞社)
当時、下級の幕臣が貧困から脱却する唯一の方法は、学問を身につけ、登用試験である学問吟味に合格して役に就くことであった。南畝もこのような志を抱いて学問に励むべく、8歳の時には多賀谷常安に漢文の素読を学ぶ。南畝の俊秀ぶりに、多賀谷は自身の師・内山賀邸(がてい)のもとで学ぶように勧め、15歳で入門。内山は、江戸六歌仙といわれた和歌の名手であり、学問は和文漢文を兼ね、狂歌も好んでよむ人であった。永井荷風が「南畝が諧謔(かいぎゃく)の天才を夙(つと)に狂歌狂詩の類に発揚したるは其師(そのし)賀邸の薫化(くんか)によれるや明なり」と評したように、南畝の狂歌・狂詩・狂文に関する才能には賀邸門下のおおらかな気風が影響していよう。なお、明和2年(1765)には父に同じく御徒として出仕している。
明和3年(1766年)、18歳にして最初の著作『明詩擢材(みんしてきざい)』を出版する。この書は中国の明詩(みんし)を題材にした作詩の用語集で、幼い頃から漢詩文に親しんできた南畝らしい著作である。この頃、荻生徂徠(おぎゅうそらい)の高弟・太宰春台(だざいしゅんだい)に学んだ松崎観海(かんかい)に入門、漢学をより深く学ぶ。
順調に儒者への道を歩んでいたが、戯作文学者としても名を馳せていた平賀源内と出会い、『寐惚先生文集(ねぼけせんせいぶんしゅう)』(明和4年・1767年)を刊行することで狂詩・狂詩作者としての道を歩むこととなった。世相をするどく指摘したこの書が、爆発的人気を博したからである。
以降、『唐詩選』のパロディー『通詩選』、洒落本『甲駅新話(こうえきしんわ)』、狂歌集『万載狂歌集』などを発表するが、一転、寛政6年(1794年)には学問吟味を首席で合格して支配勘定となり、大阪銅座詰、長崎奉行所詰を歴任、御徒身分からの脱却を実現した。
文政3年(1820年)、詩集『杏園詩集』を出版する。日野龍夫が「南畝は、青年期に託した浪漫的な夢を、いつまでも捨てなかったのである」と述べているように、晩年にさしかかった南畝としては自身の著作を遺したいと考えたのであろう。文政6年(1823年)4月、死去。墓所は日蓮宗本念寺(文京区白山)である。